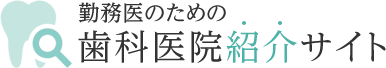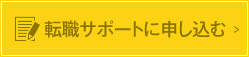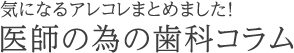歯科医師の職業病とその対処法 予防のためにできること
眼精疲労

また、近年では電子カルテ化が進み、診療カルテ入力のほとんどをパソコンで行うようになりました。診療で目を酷使し、診療の合間にパソコン上の細かい文字を見ながら入力するのですから、目への負担は大変大きなものです。
さらに、ホワイトニングやコンポジットレジン充填など、強い可視光線を用いる治療においては、網膜に軽い火傷を負うこともありますので厳重な注意が必要です。
眼精疲労から、肩こりや偏頭痛が起こることもありますので、以下に挙げる対処法や予防法を継続的に行うと良いでしょう。
■温湿布
軽く目を閉じ、緊張を解きます。目の血行をよくするため、熱めのお湯で絞ったタオルで目を覆います。最近では、電子レンジで温めるタイプの商品もありますので活用すると手軽にケアできます。
■目の体操
その① クルクル体操。眼球をクルクルゆっくりと回します
その② ギュッパ体操。目をギュッとつむりパッと開けます
その③ パチパチ体操。目を閉じたり開いたりをくり返します
その④ ピント合わせ体操。近くのものを10秒見つめた後、遠くをぼんやりと1分見ます
■ツボ押しマッサージ
目の疲れをとるツボは、眼窩に沿うように上下左右にあります。1か所につき5~6回軽く指圧しマッサージします。
■メガネやコンタクトレンズの矯正器具のチェック
度数の合っていないものを使うことで、かえって目に負担を掛けていることもあります。近視や遠視、乱視などの検査を定期的に行い、適したメガネやコンタクトレンズなどを使用します。
■適度な休息
口腔内やパソコン画面を凝視する時間を、できるだけ短くします。長くなる場合は、小休止を意識的に挟み、窓の外の遠くの景色を見たり、軽く目を閉じて目を休めるようにします。
■環境の整備
部屋の明るさやエアコンによる乾燥など、目にとって悪い環境も疲労の原因となりますので、可能な限り整えます。
■可視光線や切削片、粉塵を防護
治療に適したメガネやゴーグルを、面倒がらず必ず交換しながら使用するよう心掛けることも大切です。
■眼精疲労の回復に効果のある栄養素や食品の摂取
ビタミン類やブルーベリー、黒酢、青魚、ニンニクなどが良いとされています。食品で補いきれない場合は、サプリメントを利用する方法もあります。
■目薬の活用
多種多様なものがありますが、充血、かすみ、ドライアイなど、目の症状に合わせて選択し適宜使用します。
腰痛

特に高齢者の治療の際は、むせ易く誤嚥の危険性もあることから、どうしても術者側が高齢者に体勢を合わせる形になることが多くなります。
<対処法>
■ツボを押す
原因となる疾患が特定できない、慢性化した腰痛に効果が期待できます。ぎっくり腰のような急性の腰痛や、椎間板ヘルニアや骨粗鬆症などによる腰痛には、不向きです。
整体院や鍼灸院において専門的な施術を受けると、さらに効果的ですが、小まめに自身で行うことで痛みを軽減できます。押し方は、息を吐きながら指の腹で5秒ほど押し、息を吸いながら5秒ほどかけて力を抜きます。少し痛いけど気持ちがいい位の力加減で、ゆっくり行うことがポイントです。ツボ一か所あたり5~10回ほどくり返すのがちょうど良いのですが、体調によって回数を調整してください。
その① 手の甲にあるツボは2つあり、人差し指と中指の間から、手の甲の中央あたりに進んだ部分にある骨の境目がひとつ目です。そして、薬指と小指の間から手の甲の中央あたりに進んだ部分にある骨の境目がもうひとつのツボです。親指と人差し指で、この2つのツボを挟むように押します。
その② ヘソの真後ろにあるツボで、背骨の突起の下あたりです。両手の中指を重ねて、女性は右手を下、男性は左手を下にします。
■ストレッチ
その① イスに深く座って手は膝の上におき、ゆっくり息を吐きながら膝に胸をつける気持ちで5秒お辞儀をし、ゆっくり戻ります。
その② イスに深く座って手は膝の上におき足を組み、ゆっくり息を吐きながら膝に胸をつける気持ちで5秒お辞儀をし、ゆっくり戻ります。足を組み替え同様に行います。
その③ イスに深く座って息を吸いながらゆっくり片足を抱え込み、そのまま5秒保ち息を吐きながらゆっくり戻ります。もう片足も同様に行います。
<予防法>
日常的に、腰に長時間負担をかけることのないよう、アポイントを調節するなどの工夫をします。また可能な限り患者様に協力を求めます。
■筋力アップ体操
その① ヘソのぞき体操(腹筋を鍛えます)
仰向けに寝て両膝を立て、手をお腹の上に乗せます。息を吐きながら、ヘソを見るようにゆっくりと上半身を起こします。そのまま腹筋を意識しながら数秒保ち、ゆっくりと戻ります。
その② お尻の上げ下げ体操(お尻の筋肉と背筋を鍛えます)
仰向けに寝て両膝を立て、手は開いて横の床につけます。息を吐きながら、お尻と背中を少し持ち上げてそのまま数秒保ち、ゆっくりと戻ります。
その③ 片足上げ体操
仰向けに寝て両足を伸ばし、手は頭の後ろで組みます。片足を膝は伸ばしたままゆっくりと10~20回上げ下げします、もう片足も行います。
人の口元が気になる(番外編)
このように、口腔内の病気を診る歯科医師には、歯科医師特有の職業病があります。「医者の不養生」とならないよう、対処法と予防法を日常生活に上手く取り入れて元気に診療しましょう。